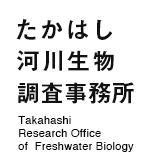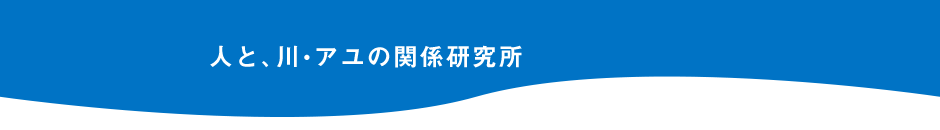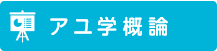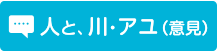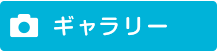環境を直す技術
更新日:2013年10月
「エコ」氾濫の狭間で
1992年、リオデジャネイロでの環境サミット。当時12歳の少女だったセヴァン・カリス=スズキさんが「直し方も分からないものをこれ以上壊すのはもうやめて」と訴えた。「直し方も分からないもの」というのは、地球環境や絶滅しつつある野生動物のこと。こういった環境問題の解決に向けて、我々は確かに努力をしている。「エコ」という言葉の氾濫はその象徴と言える。
 しかし、エコと言っている私たちの行動は本当に自然環境の悪化に歯止めをかけ、生き物たちの命を救っているのだろうか?少なくとも川に潜って生き物の様子を見ていると、そんなことはまったく感じられない。アユは私が子どもの頃は川の虫と呼ばれるほどたくさんいたのに、今や全国的に急激に減少している。わずか20年前は川に入って大きな石をめくれば必ずといってよいほど見つかったウナギは、今や絶滅危惧種である。むしろ生き物の減少に拍車がかかっているのではないだろうか。
しかし、エコと言っている私たちの行動は本当に自然環境の悪化に歯止めをかけ、生き物たちの命を救っているのだろうか?少なくとも川に潜って生き物の様子を見ていると、そんなことはまったく感じられない。アユは私が子どもの頃は川の虫と呼ばれるほどたくさんいたのに、今や全国的に急激に減少している。わずか20年前は川に入って大きな石をめくれば必ずといってよいほど見つかったウナギは、今や絶滅危惧種である。むしろ生き物の減少に拍車がかかっているのではないだろうか。観念的な環境保全活動
このギャップはいったい何なのだろうか?二つのことを指摘できそうである。一つは、エコと言われている行動は温暖化防止のみを目的としておりことが多く、多岐にわたる環境問題の一部の解決にしかなっていないということ。例えば、水力発電はCO2を出さないのでエコと言う人もいるが、河川の生態系に与えるダメージはかなり大きい。
もう一つは、「エコ」や「クリーン」といった言葉は耳あたりが良いために、生き物が減り続けているという現実がかえって見えなくなっているのではないかということ。「エコ」とつけば効果があると思いこみやすく、観念的な環境保護活動になっているというのは言い過ぎだろうか。
必要な検証作業
 いずれにしても、効果をきちんと検証することがこれからの課題である。
いずれにしても、効果をきちんと検証することがこれからの課題である。今の私たちの社会のあり方や自然保護の技術では、生き物と共生することは、まだ無理なようである。しかし、そうであればこそ、そのことと真剣に向き合うべきで、そこから「直す」技術が生まれると思うのである。
今、自然を復元する河川工法に真剣に取り組んで、成果を上げている技術者がいる。私も天然アユを増やすという活動の中から「直す」技術を見つけたいと思っている。