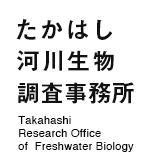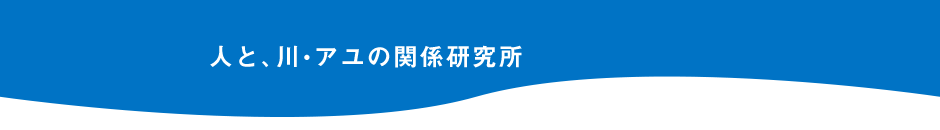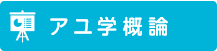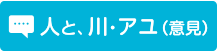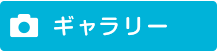天然アユを増やす取り組み(事例集)
更新日:2013年10月
事例6 産卵場整備(鳥取県日野川)
 天然アユの減少の理由は川によって異なり、同じ川でも年によって違うこともある。ただ、全国的に共通して多いのが、産卵場の荒廃である。具体的には河床材料の粗粒化(川底から小石が少なくなる現象で、ダムのある川で起きやすい)や、砂泥による礫間の目詰まりが主な原因となっていることが多い。ほっておいても産卵できないわけではないが、産卵効率は良好な産卵環境の数分の1まで低下することもある。
天然アユの減少の理由は川によって異なり、同じ川でも年によって違うこともある。ただ、全国的に共通して多いのが、産卵場の荒廃である。具体的には河床材料の粗粒化(川底から小石が少なくなる現象で、ダムのある川で起きやすい)や、砂泥による礫間の目詰まりが主な原因となっていることが多い。ほっておいても産卵できないわけではないが、産卵効率は良好な産卵環境の数分の1まで低下することもある。アユは年魚なので、産卵の失敗はやり直しがきかない。産卵環境の悪化はアユの資源変動にはかなり強い影響力を持っていると考えておくべきなのである。
鳥取県日野川は、河床材料の粗粒化と礫間の目詰まりが同時に進行した河川で、アユの産卵環境は著しく劣化していた(いる)。そこで、日野川水系漁協(佐藤英夫組合長)では2005年から産卵場の整備を始めた(写真1)。ここまでは全国各地で行われている話なのだが、佐藤さんは「産卵場整備の日」という記念日を設け(現在、10月の第2日曜日)、組合員だけでなく、釣り人や市民、行政に参加を呼びかけた。
以来、毎年100人近い人が集まって、産卵場整備を手伝ってくれている(写真2,3)。合わせて、親魚の保護期間の延長も行い、近年は天然アユも安定的に増えている(増えすぎて小型化が問題視されるほどに)。
- 産卵環境の劣化が顕著であったため、整備の効果が大きい(まずまずの産卵環境にある河川で造成しても、効果は薄く、逆に悪影響が顕在化することが多い)。
- 多くの人の参加があることで、日野川の現状、アユが減った原因を実体験として理解してもらえる。
- 産卵場整備はデメリットも大きい。その必要性を十分に検討したうえで行って欲しい。